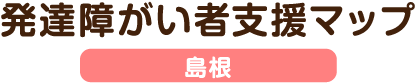発達検査と知能検査、学力と知能
子どもの発達相談でより精密な情報を得るために、発達検査や知能検査の受検を勧められることがあります。これらの検査を受検することで診断が下されたり、進路が決定されたりしてしまうのではないかと不安に感じる方もいますが、そのようなことはありません。発達検査や知能検査によって得られた情報をもとに、子どもたちの生活をよりよく整えることができます。
この記事では、発達検査と知能検査について説明し、混同されることの多い学力と知能についても解説します。
発達検査と知能検査の違い
①検査が計測する対象
発達検査とは、読んで字のごとく『発達』を調べる検査です。辞書的な『発達』とは「受精から死に至るまでの人の心身の変化の過程」と言われます。よく似た『成長』は身体の量的な変化のことであり、一方『発達』は機能的な成熟をさすことが多いです。つまり、『背が伸びた』『体重が増えた』は成長であり、『歩けるようになった』『言葉がしゃべれるようになった』『ごっこ遊びができるようになった』などの機能的な変化を『発達』というのです。発達検査はこの『発達』を検査対象にしているので、『運動』『認知』『社会性』が主な検査対象となります。
一方、知能検査が計測する『知能』や『知的能力』は、アメリカの心理学者ウェクスラーが「知能とは目的的に行動し、合理的に思考し、その環境を効果的に処理する個人の総合的・全体的な能力である」と定義しており、今もこの定義は一般的です。
②対象者と実施方法
『発達』は老年期の衰退までも含む現象ですが、発達検査の多くは乳幼児の発達を対象にしています。乳幼児期の子どもの特徴として、課せられた問題を解かなければならないという意識に乏しく、また、人見知りしやすい時期でもあります。発達検査は問題を課してその解答をみるというよりも、年齢相応の子どもの反応が出やすい状況を設定しその様子を見たり、保護者に普段の様子を聞き取ったりして発達の様子を判定することがほとんどです。そのため発達検査の中には0歳から実施ができるものもあるのです。
知能検査では、受検者に一定の問題を課しその解答から知能を測定します。受検者の解答が必要になるため、問題に取り組める一定以上の年齢が必要になるだけでなく、言語や動作などで解答できることも必要になります。代表的な知能検査であるウェクスラー式知能検査やビネー式知能検査は2歳から可能であり、成人、高齢期まで実施可能です。
③結果表示
発達検査の結果表示方法では、発達年齢(DA:Developmental Age)と発達指数(DQ:Developmental Quotient)がよく使用されます。
発達年齢とは、発達の状態がどのくらいの年齢に相当するかを示すもので、発達検査によって計測します。
発達指数とは、実年齢のことである生活年齢(CA:Chronological Age)に対して発達年齢がどれくらいなのかを数値化したものです。
発達指数は、生活年齢と発達年齢を月齢にして下記の式で算出します。
発達年齢(DA)/生活年齢(CA)×100=発達指数(DQ)
例えば、3歳4か月(40か月)の子どもが、発達検査で3歳0か月(36か月)の発達年齢であるとなった場合の発達指数は下記の通りになります。
36/40×100=90
知能検査の結果表示方法は、知能指数(IQ:Intelligence Quotient)や偏差知能指数(DIQ:Deviation Intelligence Quotient)が使用されます。
知能指数は、検査によって得られた精神年齢(MA:Mental Age)を使用し、下記の式で算出します。
精神年齢(MA)/生活年齢(CA)×100=知能指数(IQ)
一方、偏差知能指数は、統計的手法を用いて各年齢集団における知能テストの成績分布を一定の数値に変換した知能指数です。一般的に平均100、標準偏差15になるように得点換算されています。知能指数だと、生活年齢が異なると同じ知能指数でも内容が異なることがあるため、偏差知能指数が考案されました。
例えば、知能指数=120になった花子さん(5歳0か月)と良子さん(10歳0か月)とを比較してみましょう。
花子さん
生活年齢(CA)=5歳0カ月
検査で分かった精神年齢(MA)=6歳0カ月
知能指数=MA÷CA×100
=72カ月÷60カ月×100
=120
良子さん
生活年齢(CA)=10歳0カ月
検査で分かった精神年齢(MA)=12歳0カ月
知能指数=MA÷CA×100
=144カ月÷120カ月×100
=120
全く同じ知能指数(IQ=120)なのに、花子さんは精神年齢が生活年齢よりも1歳しか進んでいないのに対し、良子さんは倍の2歳も進んでいるのです。
このように知能指数は、生活年齢の違いで数値の意味が変わってしまいますが、偏差知能指数は異なる年齢でも数字を比較することができるのです。
検査をする目的は
発達検査も知能検査も、障害を診断することが目的ではありません。子どもの発達の状態や知能の様相を詳細に捉えることで、普段の関わり方のヒントにしたり保育や教育に役立てたりすることが主たる目的です。
例えば、幼稚園にておもちゃのやり取りで友達に手が出てしまう3歳4か月(40か月)の男児A君の場合を考えてみましょう。A君は、新版K式発達検査という検査で下記の通りの発達指数が出ました。
全領域=100
姿勢運動=115
認知適応=120
言語社会=85
全領域の発達指数が100であることから、A君は年齢相応の発達年齢となりますが、運動領域の発達を示す『姿勢運動』と対象を考えたり操作したりする『認知適応』の発達指数は100を超えており、実際の年齢よりも発達年齢が高い一方で、言葉を理解したり相手に伝えたりする『言語社会』の発達指数は100を下回る85となり、言葉に関する発達年齢は実際の年齢よりも低いことがわかりました。さらに詳細に検査結果を見ていきましょう。
各領域の発達年齢を( )に示すと下記の通りになります
全領域=100 (40か月)
姿勢運動=115 (46か月)
認知適応=120 (48か月)
言語社会=85 (34か月)
3歳4か月(40か月)のA君は、『姿勢運動』と『認知適応』の領域は4歳頃の発達年齢にあるのに対し、『言語社会』の領域は2歳後半の発達年齢にあるようです。
2歳後半の幼児の特徴として、自分のことを「タロウくんはね」と名前で言うことから「ボクはね」と言うようになります。一人称(自分)の視点を獲得し始めるのです。すると、相手や物を、『自分』との関係でとらえていくようになるのです。例えば、あの女の子は「はなこちゃん」だったものが「ボクのともだち」、園で使うボールは「黄色いボール」ではなく「ボクの好きなもの」というように。すると、他の子どもが黄色いボールを使おうとすると「ボクの!」と言わんばかりに手が出てしまうことがあります。
この検査結果をもとに、以前の園では「B君と一緒に遊びなさい」と伝えていたのを「Aくんが好きなボールでB君も一緒に遊びたいって言っているよ」と伝えるようにしたところ、Aくんは『ボクが好きなボール』を尊重されたのでしょうか、以降は手が出ることが大幅に減っていきました。
このように、発達検査や知能検査は、数値を出して障害を診断したり、知能が高い低い、発達が早い遅い、を判定したりするものではなく、子どもの状態を知能や発達の点から詳細に調べることで、子どもの生活支援や対応に役立てることが目的です。
検査の内容
子どもに対して実施される検査には、知能検査や発達検査だけでなく、読み書き検査や物の見え方検査などを含む『認知機能検査』もあります。また『検査』であるため、医療機関で実施されるものと思われがちですが、医療機関で実施する検査の多くは診療報酬を認められている一部の検査であり、診療報酬が認められていない検査まで含めると、数えきれなくなってしまいます。
以下は、代表的な発達検査である『新版K式発達検査』『遠城寺式乳幼児分析的発達検査法』『乳幼児精神発達診断法』、同じく代表的な知能検査である『ビネー式知能検査』と『ウェクスラー式知能検査』について説明していきます。
新版K式発達検査
先ほど3歳4か月のA君の例で示した検査で、通称『K式』と呼ばれます。
新版K式発達検査では『姿勢・運動』『認知・適応』『言語・社会』の3領域の発達を評価します。一定の月齢ごとに分類された子どもの状態や検査課題を実施し、様子や回答をみて評価していきます。保護者からの聴取も併せて参考にします。検査結果は発達指数で表示されます。
適用年齢:0歳から成人まで使用可能とされますが、多くは1歳~4、5歳までが対象になります。生後から1歳未満までの乳児には乳幼児精神発達診断法が、児童期以降の子どもにはウェクスラー式知能検査が使用されることが多いようです。
検査時間:30分間から60分間程度になります。年齢が高いほど検査時間は長くなる傾向があります。
検査料金:診療報酬が認められる検査であるため、医療機関では保険診療(3割負担の場合)で840円となります。
遠城寺式乳幼児分析的発達検査法
通称『遠城寺式』と呼ばれる検査です。
移動運動と手の運動を含む『運動』、基本的習慣と対人関係を含む『社会性』、発語と言語理解を含む『言語』の3領域の発達を評価します。子どもの様子を観察したり、簡単なカードを使用して反応を確かめたりして評価していきます。保護者からの聴取も併せて参考にします。子どもの様子を観察しやすい課題となっており、実施時間は短時間で済みます。検査結果は発達指数ではなく、おおよその発達年齢をグラフで表示します。
適用年齢:0歳から4歳8か月まで
検査時間:15分間
検査料金:診療報酬が認められる検査であるため、医療機関では保険診療(3割負担の場合)で240円となります。
乳幼児精神発達診断法
遠城寺式と分類しやすいよう、作者の津守真にちなんで、「津守式」と言われることがあります。
「運動」「探索」「操作」「社会」「食事・生活習慣」「言語」の6領域を検査項目とします。新版K式発達検査と遠城寺式乳幼児分析的発達検査法と大きく異なる点は、子どもに課題をかして様子や反応を見るのではなく、保護者に対して個別に面接して評価していく点です。新版K式発達検査と遠城寺式乳幼児分析的発達検査法のような、検査場所に子どもを招いて検査道具を渡して反応を見る方法だと、子どもによっては普段通りの反応がでないことがあります。乳幼児精神発達診断法では、保護者面接の手法をとるため、本来の子どもに近い様子で評価ができる利点があるのです。検査結果は、検査結果は発達指数ではなく、おおよその発達年齢をグラフで表示します。
適用年齢:0歳から7歳まで
実施時間:約20分間
検査料金:診療報酬が認められる検査であるため、医療機関では保険診療(3割負担の場合)で240円となります。
ビネー式知能検査
ビネー式知能検査には『鈴木ビネー式検査』と『田中ビネー式検査』があります。
いずれも、一定の月齢ごとに分類された課題を実施し、課題正答数から精神年齢を算出します。
鈴木ビネー式検査は、総問題数は多くないため、所要時間は約30分~60分間となります。適用年齢は2歳0か月~18歳11か月となり、結果は知能指数を使用します。
田中ビネー式検査は、鈴木ビネー式検査に比べて検査問題が多いため、所要時間は場合によっては60分間を超える場合があります。適用年齢は2歳以上となり、結果は知能指数を算出しますが、14歳以上の被験者には偏差値知能指数を算出します。
検査料金:いずれも診療報酬が認められる検査であるため、医療機関では保険診療(3割負担の場合)で840円となります。
ウェクスラー式知能検査
年齢に応じて検査名が変わります。検査名についている数字はバージョン名で、2021年3月時点で下記のバージョンが最新となります。
WPPSI-Ⅲ:Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
日本語名:ウェクスラー幼児用知能検査
適用年齢:2歳6か月~7歳3か月
実施時間:40分間(2~3歳)、 50~70分間(4~7歳)
WISC-Ⅳ:Wechsler Intelligence Scale for Children
日本語名:ウェクスラー児童用知能検査
適用年齢:5歳0か月 ~ 16歳11か月
実施時間:60~90分間
WAIS-Ⅳ:Wechsler Adult Intelligence Scale
日本語名:ウェクスラー成人用知能検査
適用年齢:16歳0か月~90歳11か月
実施時間:60~90分間
以下は、児童期の子どもによく使うWISC-Ⅳを中心に説明していきます。
ビネー式知能検査が知能指数を算出するのに対し、ウェクスラー式知能検査は全ての検査によって算出する全検査IQのほかに下記4指標の得点も算出します(WPPSIは年齢に応じて指標数や指標名が異なります)。
・言語理解指標(VCI : Verbal Comprehension Index)
言語理解能力を測定します。言葉の概念を捉えたり言葉を使って推論したりする能力を測定します。
・知覚推理指標(PRI : Perceptual Reasoning Index)
非言語的な情報(≒視覚情報)をもとに推論する力を測定します。新規な情報に基づく課題処理能力を測定します。
・ワーキングメモリー指標(WMI : Working Memory Index)
聞いた情報を記憶に一時的にとどめ、その情報を操作する能力を測定します。
・処理速度指標(PSI : Processing Speed Index)
単純な視覚情報を素早く正確に、順序よく処理、あるいは識別する能力を測定します。
全検査IQ以外に4指標がわかることで、子どもの状態を詳細に知ることができ、対応を検討しやすくなります。
例えば、集団行動が苦手な小学6年生男児、Z君の場合です。担任の先生がクラス全体に向けて行動を指示しても、それとは違う動きをするのです。Z君のWISC-Ⅳの結果は以下の通りになりました。
全検査IQ=95
言語理解=86
知覚推理=104
ワーキングメモリー=91
処理速度=104
ウェクスラー式知能検査は偏差知能指数で表示するため、平均=100、1標準偏差=15となります。『標準偏差』とはデータの散らばりを示す数値で、『1標準偏差内に68%が該当する』ということを示します。言い換えると、『多くの人(68%)が検査結果85~115(100±15)に収まりますよ、つまり平均的な範囲となりますよ』ということです。
Z君の全検査IQは平均域となり、知能指数上は大きな問題は認められません。次に、4指標を見てみると、言語理解指標の数値が86ではあるものの、全4指標が1標準偏差以内にあり、おおむね平均的となります。
しかし、さらに詳細に分析すると、言語理解と知覚推理との間に大きな差があることがわかりました。このことからZ君は、言葉による説明は頭の中で想像力を補って理解することが難しく、結果、誤った行動をしてしまっている可能性があることが予想されました。
Z君には、眼に見えるイラストを使用し言葉による説明の補足をするだけでなく、「バットを振るように腕を振って」のようにイメージしやすい説明をするようにしたところ、周囲と同じように行動できるようになりました。
このように、発達検査も知能検査も発達指数や知能指数を出すことが目的なのではなく、得られた結果をもとに、どのような関わりや支援が必要かを検討することこそが目的です。検査結果の分析は専門的な知識が必要であるため、通常、検査担当者が『報告書』にまとめてくれることがほとんどです。一部の機関は口頭説明や有料での報告書作成になることがあります。報告書に決まった型はないため作成者や機関によってまちまちになりますが、一般的に下記の内容が記載されます。
・検査を受けているときの様子
難しい問題は諦めが早かった、適当に答えることがすくなくなかった、そわそわして検査場面に慣れていない様子だった、母親から離れにくかったなど。検査に臨む姿勢から、子どもがどれだけ本領を発揮できたかを推測する手掛かりとなります。
・知能指数、各指標の結果表示
全検査IQ、4指標の結果を表記します。条件によっては全検査IQではなく、一般知的能力指標(GAI:General Ability Index)が表記されることがあります。
・各指標や各問題の間で生じている凸凹の分析
凸凹が大きいと、Z君のように均整のとれた認知が難しいことがあります。得意なこと苦手なことを詳細に分析し、得意なことを利用して苦手なことを補うような支援がないかを検討します。
・支援方法の提案
検査結果を総合的に判断して、子どもがおかれている状況や生じている問題への支援方法を提案します。
どこで検査を受けられるの?
基本的に、検査を受けたいと要望しても即座に検査を受けることは難しいです。検査の実施は、専門家が「支援を検討するためには、検査の実施が必要である」と判断して初めて可能になります。まずは、専門家への相談をしましょう。
上記を踏まえたうえで、検査を受けられる場所には下記のような機関があります。
・医療機関
・児童相談所
・発達障害者支援センター
・市町村教育委員会
・学校(スクールカウンセラーや教員が実施)
・カウンセリングルーム(個人開業、大学の開設など) など
医療機関では、検査が保険診療の対象であれば、保険診療内で受けることができます。児童相談所や教育機関などの行政機関では、基本的に無料で受けられます。
個人開業や大学が開設しているカウンセリングルームは、5,000円から10,000円の実費負担になることが多いです。
機関によって実施可能な検査や料金は異なります。各機関に問い合わせましょう。
知能と学力
知能と学力には一定の関係があることがわかっていますが、知能と学力は同一のものではありません。先に述べた通り、知能は「目的的に行動し、合理的に思考し、その環境を効果的に処理する個人の総合的・全体的な能力(David Wechsler)」を言い、学力は「学校教育を通じて獲得・達成されたと考えられる知識・技能や思考力・判断力(日本教育心理学会 2003)」、「確かな学力とは知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの(文部科学省)」などと定義されます
知能指数が低くても学業成績に問題が見られないことや、学業成績が低くても知能指数に低下がみられないことがあります。
知能は環境を処理する能力であり、学力は問題解決や判断に必要な力であることから、知能や学力は進学、就職などの将来を予測する指標として重視されてきた経緯があります。しかし近年では、知能や学力などの『認知能力』では複雑な現代社会での適応を予測することは難しく、『非認知能力』の方が社会適応に重要であるとの研究報告が多くなされています。
例えば、1962~67年にかけて実施されたアメリカのペリー就学前プロジェクトでは、就学前の幼児のいる家庭に毎週訪問し長期間経過を追ったところ、介入グループとそうでないグループとで高校中退率、持ち家率、犯罪率などに大きな差が出たのです。この結果から幼児教育の重要性を指摘する専門家もいますが、重要なポイントは、知能指数には差がなかったということです。当初は介入グループと非介入グループとで知能指数に差があったのですが、年を追うごとにその差は縮まり、最終的に知能指数に差異がなくなったのです。このことから、知能以外のスキルが社会的な成功に必要であると考えられるようになりました。
現在、非認知能力は『社会情動的スキル』や『社会情動的コンピテンス』と言われ、世界的に研究や調査が進められています。『社会情動的スキル』や『社会情動的コンピテンス』には自尊心、自己肯定感、責任感、外向性など、非常に種類が多いこと、年齢や文化によって重要なスキルが変わることなどの課題がありますが、複雑な現代社会を生き抜く必須のスキルとして、知能や学力以上にその獲得を目指す教育環境が整えられていくでしょう。
確かな学力 文部科学省
日本の子供の貧困に関する先行研究の収集・評価(図表3-3 ペリー就学前プロジェクトの効果) 総務省
家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成 (訳)ベネッセ教育総合研究所 OECD 経済協力開発機構
社会情緒的能力に関する研究 国立教育政策研究所